佐々木昭美のBIエッセイ 明るく楽しくイノベーション
2011/08/22 マラソンランナー 金メダリスト高橋尚子さんの爽やかな言葉
最近、世界一を目指す日本女子スポーツ選手の活躍が凄い。振り返って思い出す一人は、2000年シドニー五輪マラソン金メデリスト高橋尚子さん。優勝した時の爽やかな笑顔と言葉を今も覚えている方は多いと思います。もちろん、国民栄誉賞受賞者です。
酷暑の8月、その高橋尚子さんの率直な語らいに接して、再び爽やかな気分を頂いた。
日経夕刊「こころの玉手箱」(8/15~19)に5日連載で執筆しています。
エッセイストと思う程流れるような文体で、トップアスリートとしての重い貴重な人生体験を爽やかに読ませてくれます。大変印象深い思いをしましたので、紹介させて頂きます。
(1)金メダリストを育てた米ボルダー~標高3500メートルの非常識な練習が絶対の自信を得た
シドニー五輪でゴールした直後、インタビューで「すごく楽しい42キロでした」と答える高橋選手(当時)の言葉を皆さんも覚えていることでしょう。私も42キロの疲労感を感じさせないしっかりした口調に「まだ疲れ切っていないのだろうか?」と驚きました。同時に、優勝した精神的高揚や余裕から発する言葉かもしれないとも思いました。
実は、激烈な練習で鍛えた体力が言わせたものと語っています。金メダリストを育てた場所が米コロラド州ボルダー。ここまではよく知られていますね。私はさらに2つの事実に驚きました。
実は、シドニー五輪の4ケ月前からボルダーの山々の中でも標高3500メートルのウインターパークで過酷な練習をしていたのです。酸素が薄くなり、「胸は万力か何かでギリギリと締め付けられているようだった。」と表現しています。小出監督に彼女が直談判して始めたものです。
また、驚くのは絶対的強さへのこだわりとその継続性です。「これだけの練習をしている人はいないという絶対の自信もついた。だから、引退する年まで登り続けることになった。」という心身統合した強さです。金メダルを取るトップランナーの基本であるフィジカルへの生半可でない鍛錬あっての精神的自信でした。しかも、引退するまで続けるプロ意識に脱帽です。
(2)植村花菜さんの「トイレの神様」に涙するおばあちゃん子
高橋尚子さんの生い立ちを初めて知りました。おばちゃん子だったそうです。
2歳まで母の実家である岐阜県飛騨高山で祖母と暮らした。両親が共働きの教師で岐阜市内が勤務先だったため、祖母に預けられたのです。その後、両親の元に戻った時、祖母も引っ越して同居し小学4年生まで一緒だった。
私は2年前に訪れた飛騨高山を思い出しました。5月のさわやかな季節に観光しましたが、冬は雪深い土地です。(BIエッセイ2009/05/07 日本再発見満喫!飛騨高山・白川郷、越中五箇山・高岡、加賀金沢訪ねた旅写真)
中学で陸上部に入った。陸上のプロなど考えられなかった時代にも祖母が応援してくれたという。陸上を続けてこられたのは祖母のお陰と思っていたが、五輪の翌年3月に亡くなった。その祖母への思いをこう語る。
「去年、植村花菜さんの「トイレの神様」がヒットした。おばあちゃんとの思い出を歌ったこの曲を聴くともうダメだ。涙が止まらなくなってしまう。」
(3)恩師の教えを素直に実行した~「3倍やって初めて人並み以上になれるんだ」
恩師との出合いの大切さを改めて痛感する出合いを紹介しています。また、それ以上に「恩師の言葉を素直に実行する」高橋尚子さんという女性の非凡さに心を打たれました。非凡と言うと、高橋さんは違うと怒るかもしれませんが。
高校2年の時出場した全国都道府県対抗女子駅伝では区間47人中45位だった。
県立岐阜商業高校の顧問だった中沢先生。恩師の言葉が人生を拓いてくれた。
「おまえは素質はないが、頑張る素質はある。人の倍やって人並み、3倍やって初めて人並み以上になれるんだよ。」
「何も咲かない寒い日は下へ下へと根を伸ばせ。やがて大きな花が咲く」
大阪学院大学の頃、5時からの放課後に2時間走った後、トレーニング室で閉門午後8時ギリギリまで筋力トレーニングを日課にした。50キロのバーベルをガンガン上げていたという。
人生の岐路を決めるターニングポイントが訪れていた。卒業後は両親と同じ教師になると決めて、教員免許も取り、教育実習も終了していた。10近い実業団からの誘いもあり、相談した恩師中沢先生の言葉は予想と反して激しかったと述べています。
「3年だけやりたいとか、駅伝に出たいとか考えてるならやめとけ。やるなら日本一目指して、小出監督のところに行くくらいじゃなければ無駄だ」
その一言で、面識のなかった小出監督を訪ね、半ば押しかけで採用してもらうことになったという。日本一、世界一目指すマラソンランナーはこうして誕生したのでした。
(4)アテネ五輪代表落選~ファンの温かい励ましに「走る意味」が変わった
2004年アテネ五輪代表に落選した。人生の正念場。弱くなるとマスコミもファンも冷たくなるとの助言に身構えていたが、待ち受けていたのは温かい励ましだったという。恐らく落胆の底にあったに違いない彼女に番記者は変わらぬ態度で接してくれたし、なによりも全国のファンからそれまで以上に手紙やお守りが届いた。それがどんなに嬉しかったか、有り難かったかは、次の言葉からしっかりと伝わって来ますね。
「この頃はもらった手紙を読んでは泣いていた。この年ほどうれし涙を流したことはない。一度もマラソンレースを走れなかったという意味では最悪の年だったかもしれないが、一人の人間として幸せを感じた年だった。」
冗談ではなく、一杯泣いたのが良かったのだろうか? もちろん、うれし涙だけではなかったでしょう。高橋さんは、「走る意味」を変え、もう一度はい上がると決断した。その胸の内を語ってくれた。
「それまでは、ひたすら速さとか強さを目指して走ってきた。金メダルを取り、シドニー五輪の翌年には女子で初めて2時間20分の壁も突破できた。現役続行こそ決めたが、もう順位や記録をモチベーションにするには難しくなっていた。支えてもらったファンに恩返しするために走ろう。そう思うと再び力がわいてきた。・・(略)・・つらいことやしんどいことも多い世の中だけど、少しずつ進めばいつか明るい場所に出ることができる。」
(5)ナイロビで見た惨状に三日三晩泣いた~アフリカの子どもにシューズ送るプロジェクト
今、高橋さんは、アフリカの子供たちにシューズを送る運動に取り組んでいます。これまでに履かなくなった運動靴やスニーカーを3万2000足集め、既に2万5000足をケニアに届けたそうです。
初めて首都ナイロビの貧民街を訪ねた時は、余りの惨状に三日三晩ショックで泣いていたとその様子を伝えています。
「街のあちこちに鼻が曲がるような異臭が立ちこめていた。ごみもふん尿も山積みで放置され、あぜ道を崩したような道を跳びはねるように進んだ。ガラスの破片も落ちていた。でも、そこに暮らす子供たちの多くは裸足(はだし)だ。
日本なら「ツバでもつけときなさい」と言われそうな小さな擦り傷が、アフリカでは命取りになる。傷口からばい菌や寄生虫が入り、破傷風などの感染症を引き起こす。現地の病院で足の親指を切断した子供にあった。「靴さえあれば防げた」という医師の話を聞いて、この活動に真剣に取り組もうと決意した。」
素直で、誠実で、一生懸命な人間高橋尚子さんは魅力的ですね。私は改めてファンになりました。
以上
(参考文献)
1.日本経済新聞(夕刊) 2011年(平成23年)8月15日~19日号
 佐々木 昭美(ささき あきよし)
佐々木 昭美(ささき あきよし)
取締役会長 総合研究所所長
経営コンサルタント(経営改善、事業開発、ビジネスモデル、 人事戦略、IPO、M&A、社外取締役)
◆ご質問・お問い合せはこちらから
専門コンサルタントへの、ご質問、ご相談等、お気軽にお問い合せ下さい。
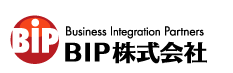
 お問い合わせ
お問い合わせ















